こんにちは、はじめまして。
地方国立大で理系分野を学んでいる大学3年生こーです。
私がなぜ自然環境やグリーンインフラに関心を持ち、TOEFLにも挑戦しているのか。専門とは少し離れたように見えるかもしれませんが、自分なりの「納得」に向かって歩んでいる途中です。今回はその背景を少しお話しします。
今大学で学んでいる生命工学の面白さ(具体的な内容や研究テーマなど)
高校の進路選択の際、生物の授業で学んだ人体の機能や代謝に興味を持ち、それを制御する仕組みが存在することに魅力を感じました。「生物本来の力をより人の役に立たせたい!」という思いから、工学部の生命工学分野に進学しました。
大学では、電磁気学や物理化学の物理分野、遺伝子工学や薬理学の生物分野、有機化学や無機化学の化学分野など、とにかく幅広い分野を学んでいます。自分の体の仕組みが少しずつ理解できるようになること、学んだ内容が繋がり合ってより深いレベルで世界を捉えられるようになることに、生命工学の面白さを感じています。
私の大学で行われている研究テーマには「遺伝子からの創薬」や「有機合成」があり、自分も学生実験の中で、制限酵素を用いた遺伝子組み換えの実験を行いました。薬づくりでは分子レベルの制御を考えますが、自然や都市環境もまた“設計できるもの”だと感じたことがあります。どちらも人の暮らしを支える“システム”であり、学んできた工学的視点は環境問題の解決にも生かせるのではないかと思うようになりました。
そこからどのようにして環境・グリーンインフラに関心を持つようになったか
学んでいく中で、特に製薬の分野に強く惹かれました。薬理学や創薬科学を学べば学ぶほど、薬という小さな存在が人の命を救うという点に、働きがいを感じました。
しかし同時に、薬を作るには非常に長い時間と多くの人手、繊細な過程が必要であることを知り、戸惑いも感じました。1つの薬を完成させるまでに約15年かかり、その間に多くの部門で試行錯誤が繰り返されます。もしある薬の開発に着手しても、それが完成する頃には目の前の患者さんには届かないかもしれない。その事実に「目の前の人の今を大切にできる仕事がしたい」と強く思うようになりました。
そんな思いを持ちながら、2024年には国内外さまざまな場所を訪れました。その中でも、フィリピン・セブ島近くの小さな島で出会った暮らしは衝撃的でした。そこでは雨水をためて生活用水として利用し、電気もあまり通っていないため、冷蔵庫も洗濯機もエアコンもありませんでした。自然のリズムに従って暮らす人々の生活は不便にも見えましたが、同時に幸せそうに生きている島の人の姿を見て、「生きていくとはどういうことか」を深く考えさせられました。下の写真はその島から見た朝日です。

また、海外に行って初めて、日本では当たり前のように安全な水道水が飲めること、ゴミが少なく整備された街がどれだけ恵まれているかを痛感しました。環境が人の心の豊かさに与える影響の大きさを実感し、自然豊かな場所にいるときの安心感や幸福感を、自分自身の体で理解しました。
こうした体験から、「自然を大切にしたい」という思いが芽生え、都市緑化や地方創生、自然と共生したまちづくりに関わることで、人々がより心地よく暮らせる社会をつくりたいと考えるようになりました。環境問題は確かに長期的な課題ですが、目の前の生活環境にアプローチすることで“今”をよくすることができる分野でもあります。そう考えたとき、この分野に関わる仕事がしたいという決意が固まりました。
将来的にどんな分野で社会に貢献したいのか
今はまだ模索中ですが、一つの問題に注力し続けるというよりは、国内外問わず、幅広い地域の課題に目を向けたいと考えています。たとえばまちづくり分野やデベロッパー、シンクタンクといった仕事を通じて、植物や川、海など自然本来の力を活かし、人が効率的かつ精神的に豊かに暮らせる社会を実現したいです。
なぜそのために英語が必要なのか
環境問題は国境を越えたテーマであり、多くの知見や先進事例が英語で発信されています。将来的には、世界の論文や現地の状況からまちづくりの新しい知見を学び、日本国内に還元する役割を担いたいと考えています。また、異なる文化の中で育まれた価値観や制度にも学びながら、現地の課題解決にも関わっていけたらと思っています。
おわりに
学んできたこと、感じたことを、TOEFLの学習とともに発信していきます。
もし、今の進路に迷っていたり、環境問題に関心のある方がいれば、ぜひ一緒に考えていけたら嬉しいです。

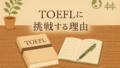

コメント